人類の内なる原初性─アリスティッポスからシュペングラーへ
書名:人類の内なる原初性
サブ:アリスティッポスからシュペングラーへ
著者:石塚正英
46判上製324頁
ISBN-13:978-4-8068-0787-2 C3030
定価3200円+税
発売日2026年1月15日(予定)
人類の原初性ないし原初的精神は現代まで潜在し、通奏低音のように文明を支えてきた、という発想を、私は研究上で重視してきた。〔歴史知〕である。その発想、視座から多くの哲学者、思想家、研究者、教育者、実践家、宗教家などを批評してきた。
今回は、大まかに言うと人物でなく地域や時局を扱う。AIや量子技術の開発競争が生みだす〔自然観・人間観〕の変貌(第一章~第三章)、そうした動向の先に予想される〔内なる原初性の再生〕(第四章~第九章)、二〇世紀後半からの大国の軍事外交と技術革新によって呼び覚まされる〔暴力と非暴力〕(第十章・第十一章)がその主軸である。ほかに、〔歴史知〕の諸相に絡む幾つかのテーマを扱っている(第十二章・第一三章)。(本書はしがきより)
■著 者 石塚正英(いしづか まさひで)
1949年、新潟県上越市(旧高田市)に生まれる。
立正大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程満期退学、同研究科哲学専攻論文博士(文学)。
1982年~、立正大学、専修大学、明治大学、中央大学、東京電機大学(専任)歴任。2020年~、東京電機大学名誉教授。
1984年、社会思想史の窓刊行委員会創立、現在に至る。
1999年、歴史知研究会創立、現在に至る。
2008年~、頸城野郷土資料室代表。
主要著作
『叛徒と革命―ブランキ・ヴァイトリンク・ノート』イザラ書房(1975年)
〔学位論文〕『フェティシズムの思想圏―ド=ブロス・フォイエルバッハ・マルクス』世界書院(1991年)
『文化による抵抗―アミルカル・カブラルの思想』柘植書房(1992年)、石塚正英著作選『社会思想史の窓(全6巻)』社会評論社(2014-15年)、『革命職人ヴァイトリング―コミューンからアソシエーションへ』社会評論社(2016年)、『地域文化の沃土 頸城野往還』社会評論社(2018年)、『マルクスの「フェティシズム・ノート」を読む―偉大なる、聖なる人間の発見』社会評論社(2018年)、『ヘーゲル左派という時代思潮―ルーゲ・フォイエルバッハ・シュティルナー』社会評論社(2019年)、『カブラル―アフリカ革命のアウラ』柘植書房新社(2019年)、『学問の使命と知の行動圏域』社会評論社(2019年)、『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸に』社会評論社(2020年)、『価値転倒の社会哲学―ド=ブロスを基点に』社会評論社(2020年)、『歴史知のオントロギー─文明を支える原初性』社会評論社(2021年)
【主な内容】
第一部 自然観・人間観の変貌
第一章 クアンタム(量子)とプシュケー(魂魄)─地に足のついた不可視の存在
第二章 量子力学は科学でなく技術である─パイディアの欠如
第三章 非ポリス的自由人アリスティッポスと非ソクラテス的思索者F・ベーコン
第四章 人はなぜ学問するか─数学者エヴァリスト・ガロアを事例に
第二部 内なる原初性の再生
第五章 パウロ・ルター・フォイエルバッハ─柴田隆行死去三年目によせて
第六章 バクーニン独裁理論とロシア原初年代記(諸公招致の物語)
第七章 マグリブ文化に垣間見える原初性─アウグスティヌスの母をヒントに
第八章 わが内なる原初性への回帰─シュペングラー『西洋の没落』を読む
第三部 暴力と非暴力
第九章 歴史知的視座からみた共同社会と政治国家の関係─『アンチ・オイディプス』をヒントに
第十章 政治的暴力と社会的抗力の区別─クルド人社会をヒントに
第十一章 資本主義の特価品AIを生みだした戦後八〇年
第四部 歴史知の諸相
第十二章 歴史知研究会の四半世紀
第十三章 ブックパーティー
(1)『土偶を読む』(竹倉史人、晶文社、二〇二一年)
(2)足達太郎・小塩海平・藤原辰史共著『農学と戦争─知られざる満洲報国農場』(岩波書店、二〇一九年)
(3)海野涼子『エステラ・フィンチ評伝』(芙蓉書房出版、二〇二二年)
(4)「現代社会を生き抜く教養教育」関連図書
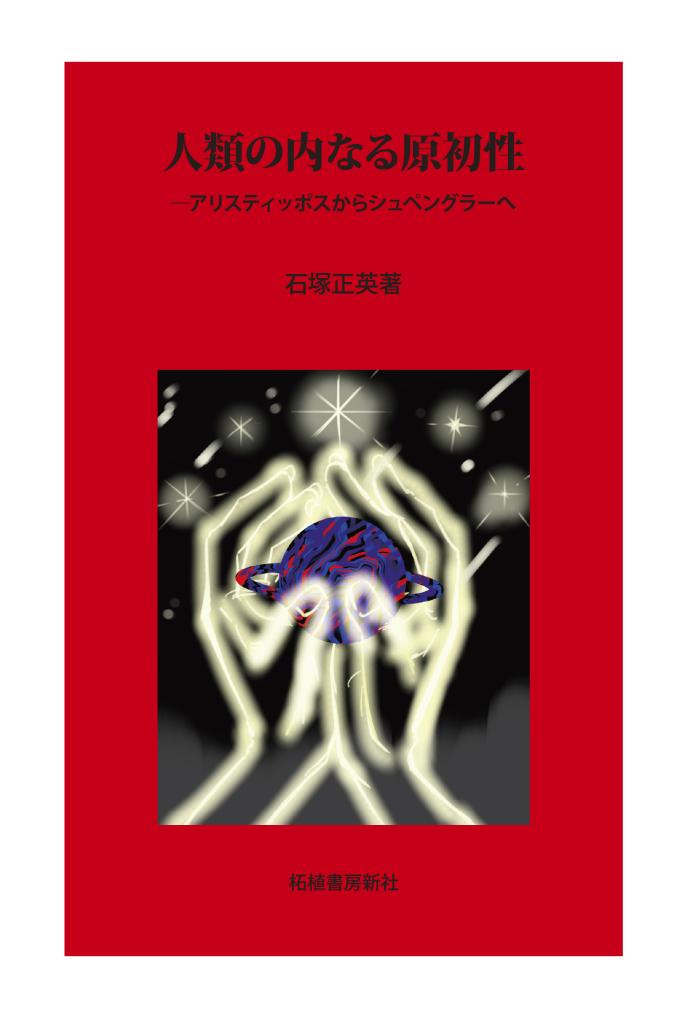
|